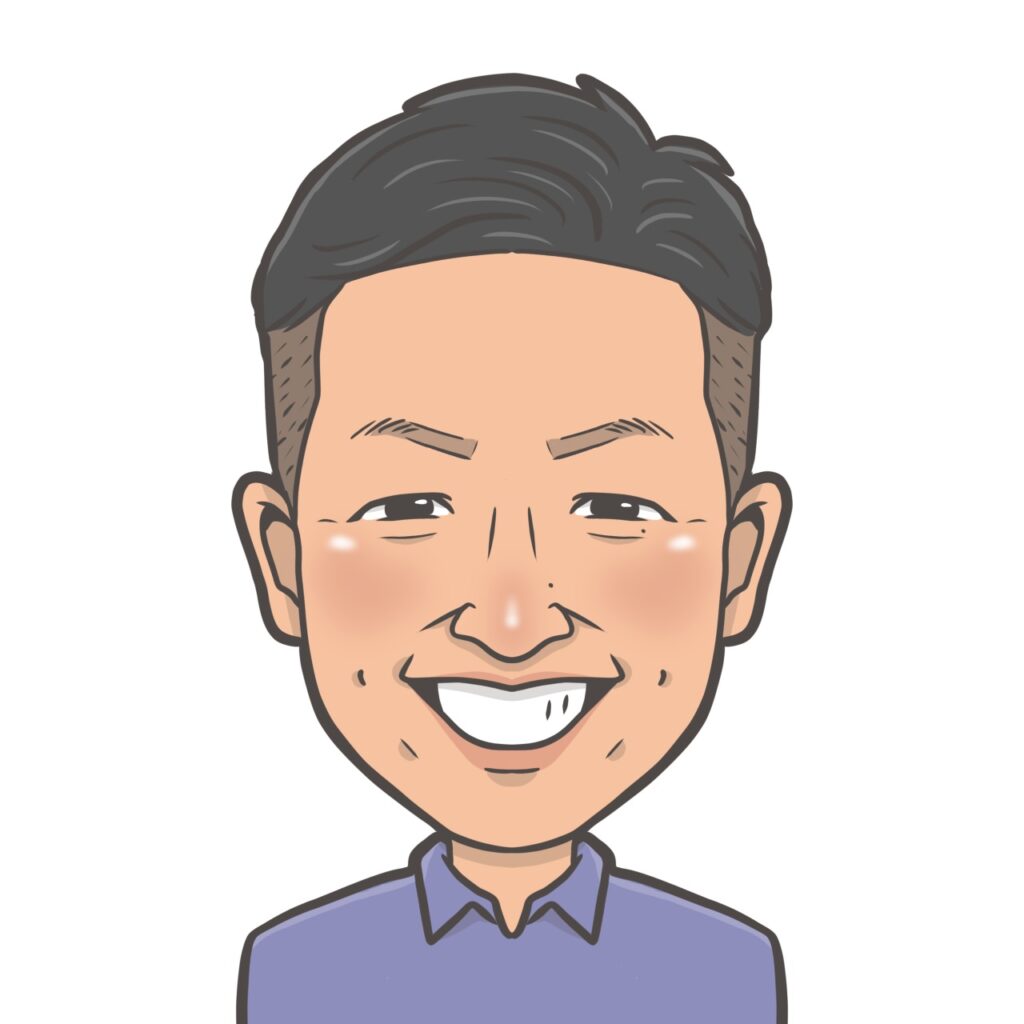凄い世の中ですよね。会社に辞職/退職を申し込む際、自らではなく第三者に交渉を委ねる訳で。
最初聞いた時には、そんなアホな!って思いましたが年々、売り上げは伸びているようで。
その道の某有名企業の哲学は、退職の意思は自分で伝えるのが望ましい。と定義しているようです。
一見、矛盾しているような気もしますが、創業者の経験から得られた深い思いが込められていそうですね。
穿った見方をするならば、稼ぐ為には何でもありかいな?と思う一方で世の中の常識を覆して一世を風靡した好例とも思います。
恐らくですが、創業者の方は何かしらの仕事を離職しようとした際、物凄いストレスを感じたのではないでしょうか。その経験をビジネスに繋げるクレバーさや先見性が垣間見得ますを伺えます。
自らの経験を元にビジネスを立ち上げたと推測しますが、ご自身の経験や主観が全て正しい。として他者を強要することなく、自分と同じ境遇の人材に対して一つの解決策を提案するとともに、更なる選択肢の提供を行っているところが素晴らしいと私は思います。
得てして、例えばですが、貴方が上司、会社側の立場の人間だったと仮定します。
これまで可愛がっていた部下が、辞めたいと相談してきました。貴方はどのように対処しますか?
ひとまず理由は聞くでしょうか。その後どうしましょう?
引き止めますか?それとも後押ししますか?
明らかに見通しが甘い場合、逆に事業計画が綿密に練られてあった場合、回答は簡単なように思います。
難しいのは、部下の夢や想いも理解できる。客観的にも決して能力がない訳ではなく、どこの組織に所属してもある程度の結果は出すだろう。かと言っていくら優秀な人材だとしても独立した後の成功が保証されている訳ではない。
と言った場合、貴方は部下を応援できますか?それとも出来ない理由を並べて不安を煽りますか?
良し悪しではなく、自らの経験や統計など確率論を考えた場合、チャレンジしてリスクを取りに行くよりも、現在置かれている立場や責任範疇でもっとできることはないのか?と安全な方向をアドバイスするのではないでしょうか?
夢や希望は分かったけれども、実社会でどれだけできるのか確証はあるのか?経営者を経験した事のない者がどうやってコーチング/コンサルをしていくのか?
明日からの生活費はどうするのか?と
どうしてもネガティブになってしまいますよね(汗
そんな時こと人の本性が見れる気がします。
できるようになるためのアドバイスができるか?それとも不安になるような(出来ない)アドバイスをしてしまうか?
大多数が後者な気がします。なぜならば、だって起業したことがないのですから、自分の中の統計に頼るしかないですものね。
あくまでも理想論かもしれませんが、
私は、起業しても無理だなって思う部下に対して、無理だ!と言うよりも今の問題点が何で、どうすれば道が開けるかも知れない?ってアドバイスを一緒に考えたいですね。
全てではないけれども厳しさやプレッシャーが成長に繋がる。と信じている世代と、論理的にコンフォートゾーンの内外で成長を促す世代の比較をしてみたいですね。
最後、他人のせいにしたくないので、私は自分の可能性を信じて信じる道を進みたいと思います。
Have a nice your journey!